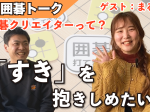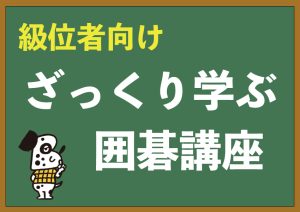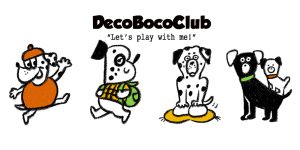囲碁をどのように上達してきたか〜初段から意識したこと〜
- 2025/4/5
- 囲碁を学ぶ

段位を上げたポイント
こんにちは。DecoBoco代表・囲碁アマ五段の井桁です。
今回は私が「これで段位を上げられた」と思うことを紹介します。
ポイントは2つあり、勉強法と対局中に意識するようになったことです。
勉強法について
級位者の頃から変えたのが、詰碁と手筋をたくさん解くようになったことです。
当時学生だった私は、実家から大学まで片道1時間をかけて通学していました。
その間、ずっと問題と向き合っていたのです。
もちろん最初から1時間解けていたわけではなく、最初は10分向き合うところから始めました。
それを行きと帰りで計20分。慣れてきたら片道20分・・と増やしていくことができました。
今のようにスマホが普通にあったら、ゲームとかSNSが気になって詰碁なんて解かなかったと思います。
まだスマホもあまり普及しておらず、暇つぶしする方法がなかったため仕方なしに解いていたというのが本音ですが、結果的には力になりました。
対局中に意識したこと
また対局中に意識し始めたのが「凝り形」です。
凝り形とは石が重複していること。その大きさの陣地を得るのに必要以上の石を使っている状態です。
この凝り形を避けるようにしたことで、少しずつ棋力を上げられました。
凝り形を考える際は、まず「二立三析」から向き合い始めました。
布石でヒラキを打つ際、もともと2つの石があるなら三間ビラキがちょうどいい広さになるという考え方です。
3つの石なら四間ビラキ、5つなら六間にヒラくと考えていきます。
反対にそれより狭くヒラくと凝り形につながります。
使っている石の数とできあがる陣地の大きさが見合わないんですね。
そうした状態をとにかく作らないことを優先しました。
凝り形を避けたことは、石が競り合った時にも役立ちました。
相手がツケてきた時、自分は右にハネたいと思ったとします。
そのハネを置いたときの状態が、程よい距離を保てるならそのまま実行する。
対して右にハネると凝り形になるようなら左にハネていく。
こうして凝り形をとにかく避けようとしたことで、反発する頻度も増えましたし、状況に応じた手を打てるようになりました。
凝り形はやっかい
凝り形は、たとえその形になっても一応陣地を作れるという点がやっかいです。
本来なら20目作っていないと見合わない広さなのに、「凝ってもいいから10目を確保しよう」と妥協する人が多いのが実情です。
当時の自分もそうでしたが、それがクセになると伸び悩みにつながります。
凝り形は不満と心に刻み、必要に応じて反発していきましょう。